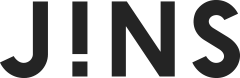メガネにおけるイノベーションを



新プロジェクトが始動する際には、クリエイティブな側面を常に加えていきたいと考えています。その分野の現況の分析から始め、まだ使われていなかったり、知られていない、しかし意味のあるものをほんの少しでも付け加えることを考える。それこそがデザイナーの務めではないかと思っています。
このことを実現するには、素材やテクノロジーを把握し、活用することが重要です。新たなプロジェクトに取り組むということは、何らかの革新を起こせるかどうかではないでしょうか。
私はいつも構築的なアプローチによってプロジェクトを進めていきます。少々極端な表現になりますが、私にとってフォルムとは二義的なものなのです。
今回のJINS Design Project も、ただ単にメガネの形態を考えるというのではありませんでした。最新の素材、テクノロジーを最大限に活かす方法とは何か?との考えのもとでプロジェクトを始め、素材やテクノロジーを最大限に活かせるものとしてのフォルムにまとめていきました。

スタート地点でJINS が挙げていたのは、「コンフォタブル」というキーワードでした。金属素材を活かすことが骨格のひとつになっていたことにも、私は興味を持ちました。たとえばアルミニウム素材。アルミニウムは鋳造でも機械で切断する方法でも実に流麗なフォルムを実現することができます。他の素材ではチタンもあります。軽くしなやかで、レーザーカッティング等の現代的な技術を活かせる素材であり、驚くほど軽量なプロダクトをかたちにできるのがチタンです。このような金属素材と他素材を組み合わせるデザインの可能性も探りたいと考えました。

構造から考えることによる
「Almost Organic」なデザイン


構造的な面に基づく発想によって十分な機能を発揮しているデザインは、それゆえの美しさを備えます。
デザインにおける私の持論は、「almost organic」、ほぼ有機的であることです。
オーガニックといっても、有機的なフォルムを意味するのではありません。メガネを構成するそれぞれの部分が有機的につながりあっているという意味です。そしてそのことによって、その物の機能を統合することができる。シンプルなものとして完成させることができると考えています。


そう、「ほとんど有機的」とは、物それ自体のなかにシンプルであることの萌芽が潜んでいることを意味するものです。
フロント部分とテンプル部分をつなぐヒンジの部分を例にしてみましょう。ヒンジの部分で全体のフォルムの流れは一度とぎれてしまうわけですが、双方の関係性を大切に、可能なかぎり連続するイメージに仕上げられる方法を模索しました。またこのヒンジは、最新テクノロジーを駆使してつくられています。その過程には複雑な技術が内包されますが、そうした複雑さを見せるのではありません。最新技術はシンプルさを手に入れる方法として活かされるべきだと考えます。その結果としてユーザーにとっての使いやすさがかたちとなり、軽やかな存在となります。顔にかけるものであるメガネは2 つの面での軽やかさが大切です。物理的に軽いということと同時に、視覚的に軽やかで大仰なものにはならないということが、メガネでは特に重要です。
デザインは「Good relations」を探ること
「almost organic」を探ることは、「関係性」の探究です。このことでは、「Good relations create good ideas」(良い関係性が良い発想を創造する)と考えています。
さまざまな関係があり、それぞれに生じうる制約がもちろんありますが、ディテールから幅広いところまで、多様な関係性を考えるのが、まさにデザインですから。
2016年春にJINS からこのプロジェクトの話をいただき、ミラノにある私のスタジオで息子のフランチェスコと3Dプリンターでヒンジのプロトタイプの制作まで進めたのは7月のことでした。私にはメガネに対する明快なイメージがあったのでそこまでは短時間で進めていきましたが、ディテールの関係性を考え、つくり込んでいくその後の作業には長い時間を費やしています。プロトタイプでの検証を通して気づくことは多々あります。考えて動く、動いたら考える。手を動かすことと考えることのサイクルが大切です。
JINS とのやりとりでとりわけ印象に残っているのは、そのつど細かな点に丁寧に、繊細かつ正確に対応してくれたことでした。
「テンプルの幅をより細くすることで、より軽やかに見える」といったアドバイスも一例です。
カラーリングに関しても例外ではありません。メガネの色はデリケートで、カラーパレットで色を選んでも、メガネに仕上げてみるとどうもおかしいと感じることがあります。今回、細かなリサーチを重ねたうえで、各デザインにおける色合いの統一ができたのもJINS の高い技術力があったからこそ。金属素材を塗装したといった印象ではなく、素材の特性を活かしたカラーリングとして、エレガントな姿にまとめることができました。
プロジェクトの過程では予測できない状況も多々生じるものです。どう解決していけるのか、それもまたデザインプロジェクトの醍醐味ではありますが、適切なパートナーと進められるかどうかが実に重要なことです。

Alberto Meda's Point of View : Innovation and Lightness

私自身は素材やテクノロジーとともに、科学の領域におけるイノベーションにも関心があります。そのうえで探究したいのは、やはり独創的なアイデアです。意味が備わっていることが肝要ですから伝統をないがしろにするということではありませんが、歴史のうえにある現在をちょっと斜めから見てみよう、違った角度から見てみよう、というのが、デザインにおける私の姿勢です。
建築デザインや現代アートにも関心があります。構造については建築分野での試みも興味深いですし、ことばで表わせないものの表現を行っている抽象芸術にも興味があります。
私自身が大切にしている「軽やかさ」については、ファウスト・メロッティはじめとするアーティストたちもとりくんでいますね。建築家のジオ・ポンティも視覚的、美的な価値としての軽やかさを表現していました。こうした他分野の作品に触発されることもあります。
もっとも、私自身が「軽やかさ」にこだわるのは、デザイナーとしての最初のプロジェクトが照明器具だったからかもしれません。照明器具とは光をコントロールするものですが、光とは形のない非物質。照明器具においては軽やかなものである必要があります。でなければ、光という非物質性と矛盾することになってしまう。この経験が、私のデザインにおける大きなパラダイムになっていると思います。

「オリガミ」は折りたたみ可能、暖房機能に加えてプライバシーを守るという心理的な面も考えられている。2018年、すぐれたデザインに贈られるイタリアのコンパッソ・ドーロ賞に輝いた、「ステップ・バイ・ステップ」は床置、壁掛けの双方で使用でき、濡れたタオルをトースターのようにはさむことで乾燥させることができる。アルミ二ウムの押出し成形でつくられており、数種類の高さから選択可能。ラジエターのフィンは斜めに設置されており、連結してもつなぎ目が見えず、全体としてひとつのヒーターに見えるように配慮がなされている。
デザインとエンジニアリングの関係性、
デザインと社会との関係性


関係性ということでは、デザインと社会の関係も忘れてはなりません。私自身のプロジェクトには企業と進めているもの以外のものもあり、安全な水を得られない国で飲料水を得るためのソーラーボトルなどはその一例です。ひとりのデザイナーとして世界のすべての問題を解決できるとは思っていませんが、社会の課題を解決していくこともまたデザインに携わる人間の使命であり、そのことにおいても技術力やエンジニアリングの力を駆使していければと考えます。
しかし、技術に関しては大きなパラドクスがあることも忘れてはなりません。私たちの日常生活において、最新技術が必ずしも課題に対して十分に寄与できるというわけではないということです。意外なところに問題解決の方法があり、問題そのものが別のところにあったりもします。大切なのは、問題や課題は何であるのか、必要とされるのは何であるのかを理解すること。そのうえで、適切な知恵や知識を導入していけること。そうやって対象に向き合うことがデザインに携わる人間の使命ではないでしょうか。
JINS では、ブルーライトをカットする「JINS SCREEN」や、 高い保湿効果が実現されている「JINS MOISTURE」のように、メガネをかける人々の健康や日々の生活の質を高める手段そのものの創造がなされていますね。そうした情熱をもつ皆さんとの今回のプロジェクトは実りある交流ともなり、想像していた以上に喜びに満ちたものとなりました。

「uno」から「Quattro」までどれも満足のいく仕上がりです。私自身がまず使いたいのは…… これはやはり、ひとつにしぼれませんね( 笑)! まず、「Meda Quattoro」を読書用に。カラーリングの仕上がりが最も気に入っている「Meda Uno」はパソコンでの作業の際に使ってみたいと思っています。